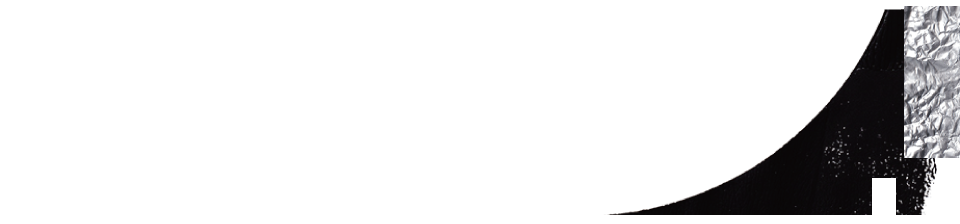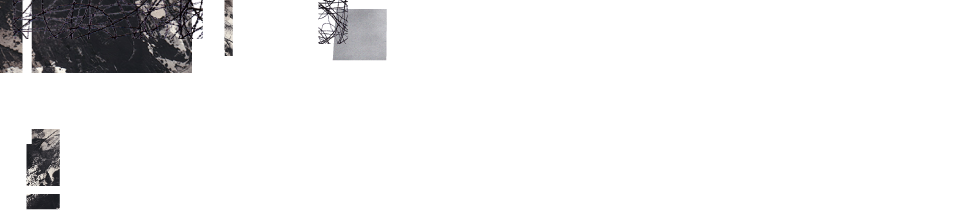工芸・鋳金
彷徨うからだ
ー鋳造によって浮かびあがる

私たちは、日々成長する社会の発展の恩恵を受け、より高水準の生活を手にしている。現代社会における技術の進歩は目覚ましく、その発達に合わせて社会は急速な変貌を繰り返している。そして現実世界のみならず、ARやVRの発達により、私たちは肉体という器から精神を切り抜き、仮想現実との間を行き来することも可能になった。この便利すぎる世の中において、時に自分は何者にでもなれるような考えに陥ることがある。しかし、精神と肉体の均衡が崩れつつある状況で生まれる考えが幻想に過ぎず、結局のところ自分は自分にしかなりえないのは、現実世界での私たちが、自らの身体の束縛から逃れられないからである。社会が生命のように発展する一方で、私たちは生まれながらにして着実に終焉へと向かい、いずれその生を終える。つまり、社会は人間の存続が続く限り無限だが、私たちの身体は有限であると言える。
現代社会においてなお、身体が有限である事を私が再認識するきっかけとなったのは、2017年に腰椎椎間板ヘルニアを発症した時だった。腰部の激しい痛みから始まり、腰椎間に飛び出した椎間板が神経を圧迫し、半年間ほど痺れを伴う痛みを左脚に感じた。歩くという基本的な動作さえ、杖を必要とするほど困難になり、手術後も後遺症で日常生活に違和感と痛みを感じた。この左脚の「通常」の感覚を失った経験から、精神と肉体の相互関係を再確認したのだった。
肉体に起こった変化の蓄積は、感覚にも影響を及ぼし、現実での動作が意図した動作とかけ離れるたびに、肉体と精神の間に感覚の差異が生じた。当たり前の動作ができなくなっていく状況のなかで、肉体と精神が結びついた身体という存在が、不明瞭になっていくのを感じた。哲学者の鷲田清一は、著書『悲鳴をあげる身体』の中で次のように述べる。
わたしの身体は、わたし自身はそのごく限られた一部しか見ることができない。ということは、わたしたちにとってじぶんの身体とは、想像されたもの、つまりは〈像〉(イメージ)でしかありえないということだ。言い換えると、見るにしろ、触れるにしろ、わたしたちはじぶんの身体にかんしてはつねに部分的な経験しか可能ではないので、そういうばらばらの身体知覚は、ある想像的な「身体像」をつなぎ目としてとりまとめられることではじめて、一つにまとまった全体として了解されるのだということである。
鷲田清一は「身体」という言葉を、「からだ」と読む。そもそも「からだ」という言葉は、「身体」「体」「軀」「躰」と様々な形で記される。その存在について、自身が知覚できる情報自体が不明瞭であるのなら、私は自分の身体を完全な形では永遠に理解しえないだろう。変化し続ける精神と肉体の間に揺れる私たちのからだは、現実という果てしない夢の中を彷徨っていると言える。そのため本論文では、「からだ」が「不完全」であることを改めて認識することで、現代社会における「からだ」のあり方ついて自他の作品を通して考察する。
本論文は全3章で構成される。
第1章「彷徨うからだ」では、自身の抱える「外的または内的コンプレックス」について言及し、「肉体」と「精神」が不安定な状態にあり、そのため私たちの「からだ」は「不完全」であること。しかし一方の「完全」という概念もまた、その定義は不明瞭であり、「不完全」と「完全」の間に明確な境界は存在しないことを論じる。
第2章「融合と装飾」では、そうした「不完全」と「完全」の「境界」を表現するために用いる「鋳造」という行為が、その制作過程において様々な「境界」を「融合」する行為であることを論じる。そして「金属」という素材と、その表層に「装飾」として刻まれる「加飾」や「痕跡」が、私たちに「幻想」という魅力をもたらすことを示す。
そして第3章「提出作品」で、提出作品の解説を交えながら、現代社会における「からだ」のあり方について論じ、人間が人間たりうるためには「彷徨う」行為が必要不可欠であることを述べる。