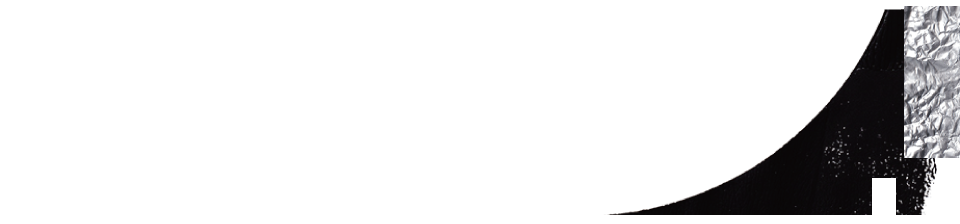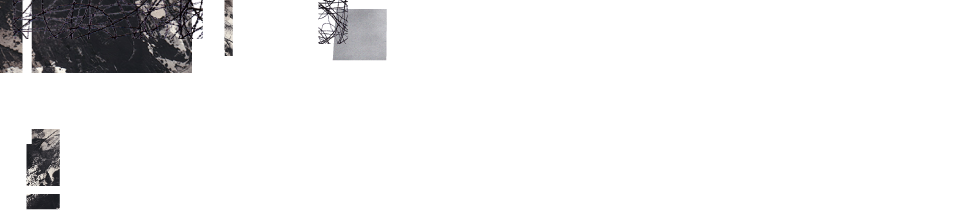美術教育
芸術的知性
ー美術教育の再措定

本論文は、芸術表現を「芸術的知性」による思考と位置づけることで、美術および美術教育を批判的に検討し、再措定することを目的とする。
こんにち、拡張を続ける芸術現象と美術科教育において、共通する芸術概念は示されていない。そのような状況は、芸術、美術教育の実践や議論において大きな障壁となっている。
序章では、研究の目的と方法を示した。芸術とはわたしたちにとって必要なものだろうか。芸術作品の鑑賞や制作をなぜわたしたちは続けるのだろうか。美術教育が公教育で必須とされる根拠とは何だろうか。そのような素朴な問いに答えるために、わたしたちは芸術に関して原理的なレベルで思考する必要がある。
第1章では、思考—世界のありようを二つの布、織物とフェルトとして思考した。織物は条里空間、王道科学であり、フェルトは平滑空間、マイナー科学である。わたしたちはそれらを〈科学的知性〉と〈芸術的知性〉と名付けた。
第2章では、領土の外に広がるカオスに抵抗するために、領土化の歌、リトルネロを歌うこと、そしてそれをひとつの芸術であることを指摘した。リトルネロは調和と秩序の力=ムーサの力を要請する。ムーサのリトルネロは詐術としての力も持ち、わたしたちを支配するものでもあった。それは王道科学と密約を結んでいる。
第3章では、その支配から逃れる力として、脱領土化としてのセイレーンのリトルネロを描き出した。セイレーンはムーサの娘としてその力を引き継ぎながらも、その秩序だった調性から逃れる力を有しているが故に怪物として描かれていた。ムーサは記憶を王道科学に引き渡すことで国家形成の神話化に加担し、セイレーンはそこからこぼれ落ちるすべての記憶を想起させようと試み続ける。
セイレーンがリトルネロを歌いだす契機を二重の親類性による「芸術の論理」にみた。また、セイレーンのリトルネロとしての芸術はわたしたちに謎を問いかけるが、それが問いとなるのはセイレーンと王道科学との密約によってである。その問いは暗闇のなかに向かい、わたしたちの思考の極限に目を向けさせるのである。
第4章では、「芸術の論理」は「夢の論理」と類似するものであり、それはフェルト状の布を作り出し、私はフェルトのヴェールに包まれることで夢を見て、また夢を見ることでヴェールを作ることを描き出す。夢はヴェールの内で、ヴェールと共に見られる「〈ヴェールによる覆い-覆いの剥奪〉なき出来事の思考」である。ヴェールは芸術=〈まったき他者〉の到来のための場である。
また、ヴェールは形象であると同時に物質=事柄であるということを指摘する。芸術作品は終着点・目的地へと至ることで完成するのではなく、「まったき他者」=芸術の到来をもって「フィックス」するのである。観る者はそこでモノとつくり手とイメージとが絡み合ったフェルトの抵抗に出会う。それは非同一性の経験であり、鑑賞者はそこで自らのフェルトを作り、それに包まれ夢見るように思考するだろう。
終章では、それまでの思考を踏まえ、美術教育を〈芸術的知性〉の教育として再措定する。美術教育をムーサのリトルネロの教育と考えれば、「無限に実験を繰り返して自分を作り上げること」としての陶冶としての教育であると言える。そこで重要なことは、子供たち自身がカオスとしての「自然」に触れ、その危機的な状況においてリトルネロを歌うという経験である
だが、ムーサのリトルネロは過去と未来、わたしたちの存在を一つの消失点に収斂させることにも通じる。また共有された領土は、領土の内に子供たちを閉じ込め為政者の詐術と文化産業的な享楽に陥らせてしまうことに繋がる。そこで、ムーサのリトルネロの力に対抗できるものとしてのセイレーンのリトルネロが公教育で行われる必要性を指摘することができる。セイレーンのリトルネロによる脱領土化の経験は、芸術作品の内に自然美を見出す経験であり、翻ってわたしたち自身の内に、また世界の内にカオスとしての自然を認めるまなざしの経験となる。
また、美術表現を造形言語によるものと位置づけ、それを日常言語としての「合理的論理的言語」と芸術言語としての「詩的言語」の使用法を指摘し、〈芸術的知性〉の教育を「詩的言語」の教育として位置づける。
〈芸術的知性〉としての美術教育はムーサのリトルネロとセイレーンのリトルネロという二つの矛盾の間で引き裂かれそうになりつつ、あるいはどちらかに矮小化される危険性に曝されつつも、その間で留まり続けようとするしかない。この矛盾を含み、解決されることのない事柄、一義的にはっきりとした位置と意味を持つことができないということ自体が芸術の性質なのであり、それを思考し実践し続けることができるものこそが、芸術的知性であると言える。