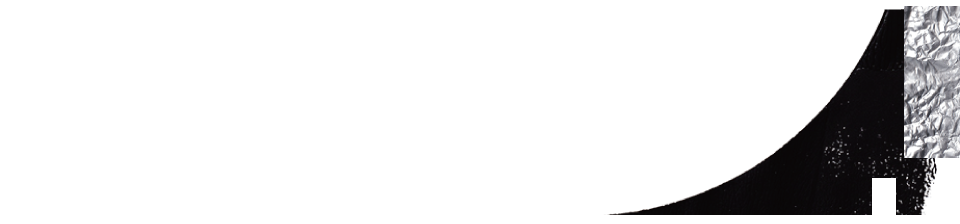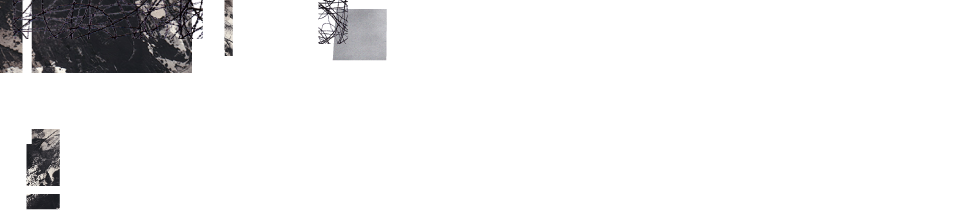保存修復・日本画
尾形光琳筆「松島図屏風」(岩崎小彌太旧蔵)の研究
—想定復元模写を通して—

本研究は、尾形光琳筆「松島図屏風」(旧岩崎小彌太蔵)の想定復元模写通して、模写に際して生じる特有の思考や制作工程について検証し、創作と模写制作の相違点を明らかにするものである。
第1章では、研究対象作品に関する先行研究と光琳の画業における位置付けについて確認した。尾形光琳筆「松島図屏風」(岩崎小彌太旧蔵、以下「光琳本」)は、江戸時代中期に活躍した絵師である尾形光琳(1658〜1716)が俵屋宗達(1570〜1643)筆「松島図屏風」(フリーア美術館蔵、以下「宗達本」)をもとに描いた模写で、のちに岩崎家別邸に所蔵されていた時期に関東大震災で焼失したとされ、現在では白黒図版の記録のみが残る。本作は光琳が宗達を写した最初期の作品で、原本と図像が酷似するため学習の目的が強かったとされる一方、焼失前の記録には宗達本と彩色や表現に明らかな相違があるという証言も残されている[1]。
また、本作の制作は直後に描かれた「燕子花図屏風」にみられる光琳独自の画風形成の契機となったという見解もある。他にも、本作を含む光琳の模写についてはこれまで、原本との相違点を光琳特有の改変と捉え、そこに光琳の独自性があると語られてきたことがわかった。
第2章では、現存する資料をもとに宗達本との具体的な比較を行った。その結果、岩や松の部分には若干の差異が認められるものの、波の部分では原本と精度の高い一致が見られた。そのため、原本を傍らに置いて写した臨模ではなく、原本の上に薄い和紙を置いて行う敷き写しの手法で大まかな形を写し、これをもとに線描と彩色を行ったと推定した。
以上の考察を踏まえて、第3章では、模写方法の実技的な検証を行った。まず、白黒図版の原寸大印刷をもとに敷き写しによる粉本を再現し、さらにその粉本に本紙を重ねて敷き写した。粉本は細い均一な線で描かれたと推定され、岩の輪郭に見られるような太い線も粉本の段階で一度細い一本の線として写されたと考えられた。そして、本紙で再び太い線に変換して描かれることで、原本とのずれが生じていたことがわかった。
そして、こうしたずれは彩色の段階で一層生じることがわかった。これは、形と彩色とでは写す際の手法が全く異なっていることから起こっていた。彩色は線描とは異なり敷き写しによって写すことはできず、一旦原本の再現から意識を離して模写自体の画面上でバランスを取らなくてはならない。つまり、色註や記憶を頼りに彩色しても、平易な印象にならないためには筆触や絵具の厚みの変化などを意識して制作する時間を要するため、その段階で原本からの変化が強いられると言えた。
模写の制作では、不明確な到達点を目指す創作とは異なり、あらかじめ到達点が定まっている到達点から合理的な逆算を行って制作工程を導き出していくことが求められる。そのため、例えば創作においては主要なモチーフから描いてバランスを取りながら制作するが、模写では細部のモチーフから描くことも可能となる。その際には、それぞれのモチーフを切り離して再構成するという思考が生じる。
そのため、創作時には空間を平面へ変換する思考が必要だが、模写の制作時には一旦均質化されたそれぞれのモチーフを空間に再構築することが行われる。こうした思考から、光琳が宗達本の模写を通して感得したのは、宗達本の図像や筆勢というよりむしろ、模写という行為のなかで宿命的に生じる、モチーフを切り分けて構成する感覚だったと考える。そしてこの模写制作に特有の経験こそが、「燕子花図屏風」に代表して「平面的」や「装飾的」などと言われるような光琳独自の表現として結果的に開花する契機となったと考えらえる。
以上を踏まえて結論では、模写における再現の不完全性とそれによって生じる変容について述べた。本研究で明らかとなったのは、これまで光琳の意図的な改変と捉えられてきた原本との相違は、模写に特有の制作工程や思考によっておのずと生じた変容であったということだった。そして、こうした事実は、日本文化における伝統的な継承方法とされ、琳派を語る上でも切り離せないキーワードである「写し」について考える上でも重要な提唱となると考える。「写し」は、図様や技法の継承だけでなく、わずかな変容を繰り返すことで新たな芸術の創造をも導き出すものとして捉えられてきたが、その変容は個人の才覚によって原本に改変が加えられることで起こると考えられてきた。しかし、本論を踏まえれば、「写し」の文化の本質は“模写の不完全性”によって宿命的に起こる変容の中に美が見出されていたことにあったと言える。
――――――――――――――――――――――――――――――
[1] 野口米次郎『日本の美術』大鐙閣、1920年、366〜367頁
明治43(1910)年の日英博覧会に出展された際の記録が記されている。