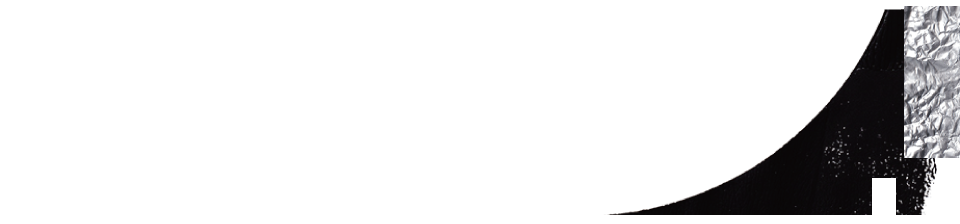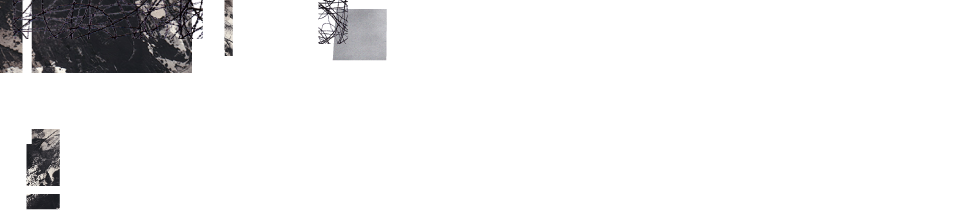油画・版画
境界の手触り
――“文字”から晶出/融解する共同体のイメージ――

本論文は「境界の手触り」と題し、社会的共同体を人工のイマジネーションの規則的反復による「社会的結晶」とみなし、その晶出(結晶化)を促す「文字」が作り出す境界のイメージについて論じる。
文字とは言語を伝達するために線や点で構成された記号である。「言語」とは一般的に音声言語と文字言語を指すが、人間社会における共同体の形成と密接な関係にあるのは後者である。筆者の制作は一貫して、伝達のための文字及び文字を媒介する複製技術を、「書く」ためではない筆記行為と、複製を目的としない版画技法という純粋な造形行為に還元することで、共同体というそれ自体が物質として存在しないものの輪郭を表出しようとする試みである。
ソシュールは、言語における話し手と聞き手が伝達する記号が表す意味は、本来的に曖昧な性質を持っているため、完全な形で概念を共有することはあり得ないとする。それでも言語活動がこれまである程度同じ意味の伝達を可能にしていることから、言語使用者にとって共通とされる部分を「平均値」として、その平均値の上に成り立つ人々の活動を、規則性と安定性の高い要素の「社会的結晶化」と例えている。自然科学における「結晶」とは、原子や分子が、空間的に規則性を有するパターンによって繰り返し配列された物質を指し、結晶化とはある均一な溶液から固体の結晶が生成される現象のことである。ソシュールの比喩を更に発展させ、言語を結晶生成におけるパターン配列に例えると、言語使用による結晶とは、複数の人間が寄り集まって作られる共同体のことだと言える。そして、その「平均値」のパターンの繰り返しが行き着く先には、ルイ・アルチュセールのイデオロギー論における「アンテルペラシオン」(良き市民であるためには何をするべきか?)という呼びかけに繋がる。これはベネディクト・アンダーソンが「想像の共同体」と呼び、メルロ=ポンティが「制度化」と呼ぶ現象とも類似するが、「結晶化」という言葉の特徴は、対象が「あるか/ないか」ではなく、「状態」が変化する可能性を含んでいる点である。
音声によるコミュニケーションは人間だけのものではないが、文字を使うのは人間だけであり、「文字」は、人為的に作り出された境界の一つだ。言語使用による対面交流でしか形成され得ない小単位の共同体は、文字とメディア、印刷技術を介することで、顔も知らない大勢の人間から成る大規模な共同体の形成を可能にした。つまり複製技術は共同体という結晶生成における触媒だと言える。「複製」と「文字」は、社会的結晶の形成の条件であると同時に、人為的に洗練し続けることで、その結晶をより大きく純度の高いものに成長させることができる。
一方、絵画における「イメージ」は、言語が作り出す境界を超越すると言われている。しかし絵画の起源、すなわち人間がなぜイメージを必要としてきたのかという根源を探ると、イメージは常に「共同体」における境界の形成に加担してきたことが明らかだ。言語が共同体という結晶の生成に必要なパターンだとすれば、「イメージ」はその仕上がりの姿を先立って提示することで、より巨大な結晶生成における補助の役割を持つ。イメージもまた、言語とは違う方法で境界を形成すると同時に、イマジネーションの境界それ自体なのである。
絵画における「イメージの帰属性」という問題は、日本人の血が一滴も流れていない著者が、幼少時から自身の「国籍」に属さないこの地で生活するうえで、常に向き合わなければならなかった問題である。移民、あるいはそれに近い「根無し草」のような立場の人間は、アイデンティティの形成過程において何らかの問題を抱えがちだ。筆者は、複数のコンテクストが入り混じるような環境において、自身で描いた一本の線にすら「これはどちら側のものなのか」という不安を常に抱いてきた。それゆえに筆者は、「描く」ことではなく「書く」(定められたパターンの繰り返し)行為を通して、イメージを摸索することを選択する。それはやがて「書く」(境界を形成する)行為から、再び「描く」(境界をなぞる)行為へと循環し、結果として水が気体、液体、固体と変化するように、文字という物質が状態変化していくようなイメージの表現が生まれる。
機械翻訳技術の発達により、言語による境界が次第に脆くなりつつあるのは確かである。しかし昨今の世界情勢から鑑みると、移民の増加や混血によって様々な既存の境界がゆらぎ、グローバルで多様性に富んだ価値観が主流になっているかのように見える一方で、実際にはその反動のように多くの国で保守的で排他的な力が働いている。それは大きな共同体が、それを形成する膜を崩すまいとしなるようにも、結晶の「純度」を落とすまいと不純物を排しているようにも見える。共同体は結晶のように強固な構造をもっていながら、常に自らを組み替えていく側面を持つ。
筆者は境界に立つ者として、変容する共同体の輪郭を常に第三者的な視点で観察してきた。その不可視のイメージの境界に、「描く」ことと「書く」ことを通じて触れていく過程を本論文で論じていく。
本論文は3章構成で論述する。
第一章は「共同体の輪郭」と題し、絵画を巡る主体-客体の考察から、筆者がどのように表現の対象を「文字」と「共同体」としてきたのかを論じる。それは、視点を固定し、透視法(遠近法)によって対象を観察して描くという、筆者が日本で受けてきた西洋式の美術教育から出発し、「現実の境界」をなぞることから、やがて言語の境界、そして共同体の境界へと移行する過程である。
第二章は「文字から晶出する共同体のイメージ」と題し、印刷技術によって拡大する共同体にとって文字がどのように機能してきたか、また共同体を内から固めようとする権力者の意思の表象としてのプロパガンダについて論じる。芸術と権力は長い間、切っても切れない関係にあり、その関係性において芸術は実用的な道具として機能する。しかし、権力対作家、あるいは全体主義対自由主義という単純な二項対立の問題のみに注目するのではなく、むしろ道具としての芸術がその機能を失う瞬間、既存の共同体の境界がゆらぐ瞬間に、筆者は表現の可能性を見出す。
第三章は「文字から融解する共同体のイメージ:提出作品「The Facets of Boundaries」と題し、文字とイメージ、「書く」ことと「描く」ことの境界、及び提出作品について、中国の文人画家、趙孟頫が唱えた「書画同源」の概念をはじめ、アンリ・ミショーやヴォルス等、文字をテーマに制作する作家を引用して論じる。これらの作家は、筆記と描画の境目がない領域で作品を作ってきた。それが「絵」なのか「書」なのかという問題の根底に、「身体」がある。